2020.8.3藤井光 ♣失われた場所としての「輝く草地」
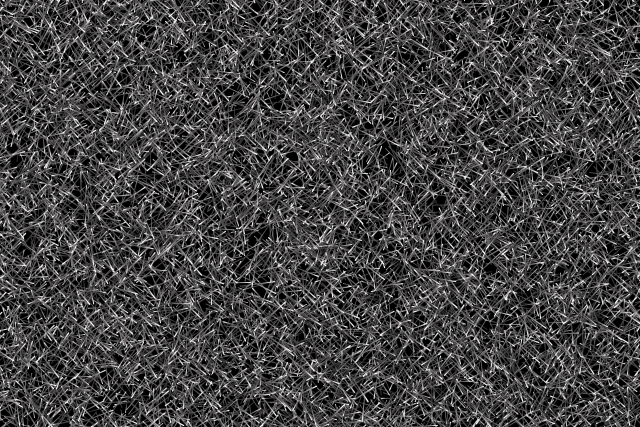
✏ 文=藤井光
2018年、アメリカ合衆国で出版された難民作家のアンソロジー、『ザ・ディスプレイスト』(The Displaced)に序文を寄せた編者ヴィエト・タン・ウェンは、こう書きつけている。
わたしには、場所を追われることから作家が生まれるのだと思えてならない。(18)
もちろん、ウェンはなによりも、みずからが難民となったのちに作家として歩み始めた経験を語っている。だが、そこから作家であること自体に話を広げようとするこの言葉は、難民や移民にとどまらず、さまざまな作家たちとの接点を作り出していく。
「場所を追われること」(displacement)。それと作家であることの結びつきを考えるとき、僕の頭にどうしても浮かんでくるのは、アンナ・カヴァンのことだ。
世界には自分の居場所などない。その端的な事実から出発して、カヴァンは忘れがたい幻想に満ちた作品を作り上げた。そのことを考えるたびに脳裏をよぎるのは、短編「輝く草地」(“A Bright Green Field”)である。「場所を追われる」という感覚が作家としてのカヴァンの核心にあると仮定してみると、この短編をめぐる謎めいた光景からは、作家の抱えた孤独の深さが見えてくるように思える。
✻ ✻ ✻
1958年に発表された同名短編集の冒頭に置かれた「輝く草地」のプロット自体は、かなり単純である。語り手である「私」が、光り輝く草地が旅の先々に現れるという現象を述べる。ある夏の日に、旅先の小さな町から見える急斜面にまたも現れた草地では、何人もの人が張りつくようにして草を刈り取り続けている。そこで語り手は、想像のなかで気がつく。そうしてひたすら刈り続けなければ、草は増殖を続け、やがて世界を覆い、すべてを殺してしまうだろう……。
なにかが、世界のすべてを覆う。それはカヴァンに固有の主題でもある。たとえば、世界が氷に閉ざされるという終末的な風景は、『氷』から「ジュリアとバズーカ」まで繰り返されている。それが「草」であるとき、語り手はそれにどう接すればいいのか。「輝く草地」は次の一文によって開始される。
In my travels I am always being confronted by a particular field. (98)
どこへ旅をしようとも、かならず現れる草地。それを記述していくにあたって、語り手は「対立」のニュアンスを含む “confronted” という単語を選んだ。語り手である「私」と、その草地は、根本的に相容れないのだ。
草地が輝いている。そのことを描写するカヴァンの文章は、「輝き」にあたる言葉を執拗に積み重ねていく。物語が進むにつれ、それは “almost incandescent” や “almost a source of light” から “emerald” や “jewel-brightness”、さらには “flare of brilliance” や “green flame” などの表現になっていく。草の描写は植物から離れて、光や宝石や炎といったイメージに置き換えられ、無機質な面を剥き出しにしていく。
自然という外界にある無機性。そうまとめるとするなら、それと向き合う語り手をはじめとする人間たちには、「生命」としての面が描かれていたりするだろうか。当然ながら、そうではない。
列車で到着した小さな町で、語り手はいつもの草地を見る。そして、通りかかった地元の男性の説明を聞き、ロープや滑車で草地に固定されているその人々が、草を刈る労働に従事していることを知る。「消耗品」(expendables)とされる労働者たちは、機械の部品のようにしてしか扱われない。草が非生物のようにとらえられるのと同時に、人間もまた無機質になっていく──労働者たちが遠くにいるせいで「人間には見えない」(dehumanized)と述べる語り手の言葉は、単なる印象にとどまらない。草地とは、草が植物ではなくなり、人間が非人間化する場所である。
✻ ✻ ✻
通りすがりの男性がどこかに去っていったあと、夜の帳が訪れるのを待つ「私」のまわりには、誰もいない。やがて訪れる闇夜に屈することなく、光を放つ草地は、独自の生命力を剥き出しにする。
I could imagine that grass might grow arrogant and far too strong, nourished as this had been; its horrid life battening on putrescence, bursting out in hundreds, thousands, of strong new blades for every single one cut. (103)
ここでは草の生命が「その忌まわしい生命」(its horrid life)として否定的に言及される。そして、「草の葉」だけでなく「刃」という意味を持つ言葉“blade”を導入し、その次の一文では “blade” を三度も繰り返すことによって、草自体の暴力性があらわになっていく。そうして、この語り手の想像において、草の生はその他すべての死と接続される。
I saw the grass rear up like a great green grave, swollen by the corruption it had consumed, sweeping over all boundaries, spreading in all directions, destroying all other life, covering the whole world with a bright green pall beneath which life would perish. (103-104)
ひたすら増殖する草の葉は、ほかのすべてにとっては破壊の刃である。それに思いいたったとき、“grass”は“great green grave”という音の連なりに合流し、はっきりと「死」の意味を与えられる。語り手自身を含むこの世界は、この脅威から逃れられないのだ。
✻ ✻ ✻
とすれば、労働者たちが草を刈り続ける、その果てしない努力は、「その他すべての生命」(all other life)が存続できる場所を確保するための、根源的な営みという意味を持つことになる。鎌をひたすら振り回す労働者たちは、草の葉という刃に対して鎌という刃で対抗しているのだ。そして、草地で命を落とせば「その場」(in situ)に葬られる。このラテン語“in situ”には、「本来の場所に」という意味もある。ひたすら草を刈り、命を落とす現場こそが、その労働者たちのすべてが完結する場所なのだ。
他のすべての生命に与えられた場所は、草と鎌の「刃」同士のせめぎ合いによって支えられている。それが世界の真理だとして、それを理解しているのは、語り手ただひとりである。物語においては、そこまで想像をめぐらせるのは「私」しかいない。そして、それは作家自身の孤独につながっていく。なぜ、自分だけなのか?
And how do I come into it? Why should I be implicated at all? It’s nothing to do with me. There’s nothing whatever that I can do. Yet this thing that should never have happened seemed something I cannot escape. (104)
この無力感に満ちた文章において、「どのようにそこに自分が入るのか」(how do I come into it)や、「どうして自分がそこに含み込まれるのか」(why should I be implicated)という表現にもまた、「場所」のニュアンスが含まれている。この世界において、どこに「私」の場所があるのか。そもそもどうして、「私」はこの世界の一部にならねばならないのか。
少し前には、労働者たちは語り手にとっては「非人間化」(dehumanized)されていた。逆に言えば、その態度によって、語り手は、草地をめぐる闘争に無関心なまま日々を過ごす「人間たち」の一員でいられた。だが、刃と刃がぶつかり合うその暴力こそが世界の根源であると気がついてしまい、無関心な集団から離脱したそのとき、語り手のいるべき場所がどこなのか、という問いからは、すべての答えが消えてしまう。
離れたところから労働者たちを眺めるほかなく、同時に、世界の成り立ちについて忘却することももはやかなわない「私」は自分の場所を永遠に喪失したという事実に繰り返し対面させられる(confronted)ほかない、想像力によって世界という圧倒的な暴力を目にした者にとって、「本来の場所」(in situ)とは何なのか。どうすれば「人間」でいられるのか。それは、ほかの誰にも見えない真理に到達してしまった作家が、みずからに発し続けた、絶望的なほど孤独な問いなのかもしれない。
〔註1〕ヴィエト・タン・ウェンの当該の文章については、『ザ・ディスプレイスト』(山田文訳、ポプラ社、2019年)から引用した。“A Bright Green Field” の英語原文は、New York Review of Books によるカヴァンの短編選集 Machines in the Head: Selected Stories(2020)から引用している。本文中での日本語訳は筆者によるものである。
❐ PROFILE
東京大学文学部・人文社会系研究科現代文芸論研究室准教授。北海道大学大学院文学研究科修了。著書に『21世紀×アメリカ小説×翻訳演習』(研究社)、『ターミナルから荒れ地へ──「アメリカ」なき時代のアメリカ文学』(中央公論新社)。訳書にアンソニー・ドーア『すべての見えない光』(第3回日本翻訳大賞受賞、新潮社)、スティーヴン・クレイン『勇気の赤い勲章』(光文社古典新訳文庫)、ヴィクター・ラヴァル『ブラック・トムのバラード(東宣出版)、ニック・ドルナソ『サブリナ』(早川書房)、デニス・ジョンソン『海の乙女の惜しみなさ』(白水社)など多数。




