2020.6.18ハーン小路恭子 リレーエッセイ(1)✍ 洪水と息切れのアメリカ──ゾラ・ニール・ハーストン『彼らの目は神を見ていた』再読
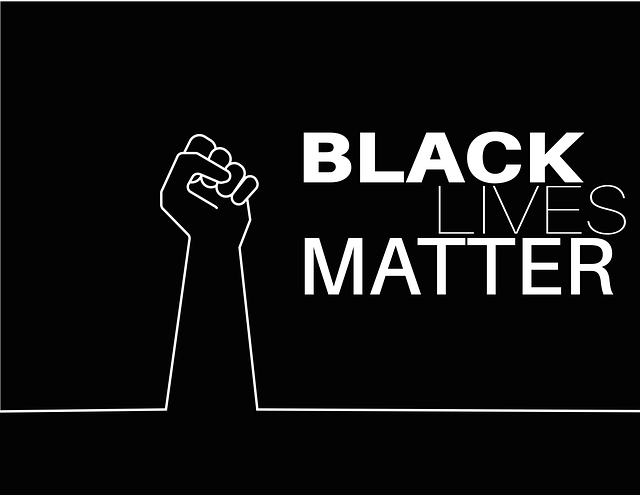
✏ 文=ハーン小路恭子
黒人女性ジェイニー(Janie)が、市街地から広大な湿原地帯へと南部の空間を移動し、さまざまな男性に出会うなかで次第に自己を見出し、人生の物語を語り始める過程を描く1937年出版のゾラ・ニール・ハーストン『彼らの目は神を見ていた』(Their Eyes Were Watching God)。
黒人フェミニスト小説の草分けと評されることも多いこの作品の、意外に知られていない側面は、ハリケーン小説としてのそれだ。豊かな暮らしを捨て、季節労働者として肥沃な黒泥土に覆われたフロリダ南部に降り立ったジェイニーは、最後の恋人となる年下の男ティーケイクと幸福な生活を送るも束の間、巨大なハリケーンに遭遇する。地域一帯に甚大な被害をもたらしたこの怪物的な猛嵐を、ハーストンは次のように活写する。「湖という怪物は寝床を離れた。風速90メートルの風で、足枷が解けたのだ。堤防を掴み取ると仮設住宅(クオーター)まで走り寄り、土地を根こそぎむしり取った。堤防を、家屋を、家の中にいる人々を、木材もろとも蹴散らした。濁流は重々しい踵を大地に振り下ろしていた」(184)〔註1〕。氾濫する湖を擬人化した黙示録的かつリアルなこの描写は、不気味なまでに2005年のハリケーン・カトリーナのニュース映像と重なり合う。高度に視覚的で、予言的ですらある筆致で、ハーストンは嵐が南部の土地を飲み込むさまを綴った。
さらに本作は、自然災害という危機が明るみに出す、決定的な社会的分断をも描き出す。近隣の町へ避難したティーケイクは、見知らぬ白人たちに銃で脅され、瓦礫の始末や犠牲者の埋葬を手伝わされる。そこで彼は、腐敗し顔の判別もままならない遺体であっても、白人であれば棺に入れ、黒人であれば大穴に放り込んで消毒のために石灰を振りかけろと指示されるのだ。「神様がジム・クロウ法のことを知らないとでもいうのかよ」と、非常時なのに、いや非常時だからこそ人種隔離を徹底させるやり口に、ティーケイクは憤る(196)。だが彼自身、嵐の到来を察知していち早く避難していくセミノール・インディアンたちを、次のように嘲ってもいた。「インディアンは何も知りゃしねえよ。知ってたら今でもこの国はやつらのものさ」(177)。
白人に倣って避難を思いとどまったティーケイクの嘲笑が皮肉に響くのは、嵐が万人に平等に訪れるものであるにしろ、救いも、埋葬ですらも、平等になされはしないということを、彼自身の被災体験がのちに証明してしまうからだ。カトリーナで最も甚大な被害を受け、長期に渡る過酷な避難生活を強いられたのは、ニューオーリンズの黒人低所得層であったことが想起される。
人種隔離の矛盾を一身に受けたティーケイクは、やがて死に至る。洪水から逃げのびる途中、ジェイニーを襲おうとした野犬と闘って頬を噛まれ、狂犬病を発症するのだ。ジェイニーは懸命に看病にあたるが、ついには錯乱状態に陥った彼に小銃を向けられる。涙ながらに、彼女は最愛の夫をライフルで撃ち殺す。狂犬病にまつわる細部は、主人公の悲劇的な愛の行く末を彩る道具立てに過ぎないようにも思える。
だが驚くほど多くの人々を死に至らしめた病と暴力にわたしたちが直面するいま、このくだりを読み返すとき、狂犬は、闇雲にひとを殺そうとする不可解で強大な力の化身として立ち現れる。狂犬病の症状としてよく知られるのは、水への拒否反応と呼吸困難である。死に際のティーケイクは(夥しい数の死体が浮かぶ汚れた存在としての)水を恐れ、首を絞められ息が詰まるような感覚に襲われる。奇しくもジェイニーは、「あの犬はただ噛もうとしたわけじゃない。ティーケイク、あいつはあたしの息の根を止めようとしてた」と語っていた。その存在は「憎しみそのもの」だったと(190)。それがどのような憎悪かは、ティーケイクの壮絶な埋葬体験が証明しているだろう。
2005年のハリケーン・カトリーナは、災害が不釣り合いなまでに黒人共同体を破壊するさまをあらわにした。2014年のエリック・ガーナーの死後、「息ができない」は、構造的な人種暴力に直面するアメリカの現実を指し示す標語となった。コロナウイルスの流行とジョージ・フロイド暴行致死事件の渦中にあって、今年その言葉はさらなる重要性を帯びている。当然ながらこれらは、ここ20年で突然に始まった現象ではない。わたしたちは歴史のうちに、さまざまに水を恐れ、息をしようと喘ぐ人々を見つける。
ティーケイクの死後、ジェイニーはかつて住んでいた町へと帰り、ことの顛末を友人に語り聞かせる。「物語の始まりには女がいて、死者を埋葬してきたところだった。闘病の末に、友人たちに枕元でみとられて亡くなった死者ではない。水浸しで、膨れ上がった者たちだ。突然に死を迎えたその目は、最後の審判に見開かれていた」(1)。銃弾を受け倒れこんだティーケイクを抱きかかえたジェイニーは、彼に肩口を噛まれていた。彼女もまた、じきに呼吸を止めてしまうのだろうか? 小説のなかに答えは書かれていない。それでも、物語ることを通してジェイニーは、生きのびてなお死とともにある、危機の時代の語り手になる──ハーストンが描いたのは、埋葬と追悼の連鎖のなかで生まれる、そのような語りの歴史であったかもしれない。
〔註1〕小説本文は、既訳を参照しつつ筆者が訳出した。
参考文献
Hurston, Zora Neale. Their Eyes Were Watching God. New Ed, Virago Press, 1986.
ゾラ・ニール・ハーストン『彼らの目は神を見ていた』松本昇訳、新宿書房、1995年。
❐ PROFILE
専修大学国際コミュニケーション学部准教授。専門分野は20世紀以降のアメリカ文学・文化で、小説やポップカルチャーにおける危機意識と情動のはたらきに関心を持つ。著書に『アメリカン・クライシス──危機の時代の物語のかたち』(松柏社)、訳書にレベッカ・ソルニット『説教したがる男たち』『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』(以上、左右社)。
✮ この著者に関連する小社刊行物




